
デザイナーは、良き“媒介者”であれ──BCGDV花城泰夢
「そもそも自分って本当に“デザイナー”なのか?と思うくらい悩みました」
取材の冒頭で花城泰夢が発した言葉は、彼のキャリアを端的に表していた。
ボストン コンサルティング グループ(BCG)において、大企業との新規事業創出を専門に行う組織であるBCG Digital Ventures(BCGDV)へ2016年にジョイン。5年が経った今、その肩書き(Partner& Director, Experience Design)にはDesignに加えてPartnerという文字が並ぶ。
現在のポジションに至るまでの間、「必要なことは何でもやってきた」と話す花城。前職では出版、オンライン英会話サービス、ゲームアプリ開発と幅広い業界で経験を積んできたが、どの環境においても自身の役割に制限を設けず「越境する」のが花城流だ。
“越境するキャリア”の先で、コンサルティングファームの中に自らの居場所を見出した花城は、これまでどんな道を歩いてきたのだろうか。
本記事はWantedly Official Profileとのコラボレーション企画です。
デザインも企画も編集も「必要なことは全部やる」
沖縄県石垣島で生まれ育った花城。ファーストキャリアは、東京の実用書系出版社だった。それも、デザイナーではない。営業を経て編集部へ異動、書籍編集者としてキャリアを積んだ。ただその頃から、すでに彼の“越境するキャリア”は始まっていた。
花城「その出版社は、『作って半分、伝わるところまでやりきって半分』というスタンスで、本を届けるために必要なことは全部やっていましたね。その中には、書店に置くPOPや、営業が使用する注文書、本の装丁などをデザインする仕事もありましたが、デザインに重心を置いていたわけでもなく。『編集』『企画』『デザイン』の三つのバランスを重視していました」
花城が手がけたデザインは評判が良く、自分の担当書籍以外も任された。他方で、企画会議には毎回10本以上の企画を持ち込んだ。ときには著者の取材に同行、自らエピソードを引き出すことも。もちろん、書籍の編集作業も手がける。文字通り、領域は問わない活躍ぶりだった。

花城「ここまでが自分の領域、という感覚はほとんどありませんでした」
そう話す花城は、自身の働き方をサッカーに例える。ポジションは決まっているが、誰が駆け上がってシュートを打ってもいいし、守りに入ってもいい。一つのプロジェクトを成功させるために、自分の立ち位置をゆるやかに動かすことで、媒介者的に役割を発揮してきたという。
そのように、枠組みを軽々と飛び越えられるのはなぜなのだろうか?
花城「共感できる想いを常に大切にしているからでしょうか。自分が担当したプロジェクトでは、いずれもビジョンに誰よりも共感し、『自分が引っ張っていきたい』という強い想いを持っていました。
例えば『宇宙授業』という書籍を担当したとき、著者である元JAXA広報の高校教諭(当時)は『子どもたちに宇宙の魅力を伝えたい』という想いに溢れていました。子どもたちのために授業中に国際宇宙ステーションと通信を繋げるなんてすごいですよね。先生の熱い想いを届けるために、自分にできることは何でもやろうと思いました」

成果が認められて最終的には編集長職を任されるまでになるも、その道を歩み続けることはなかった。花城はアートディレクターの川口清勝が率いるTUGBOATグループに転職する。2009年のことだ。
当時はまだガラケーを使う人の方が多い時代。その中で、花城はデジタルの可能性を模索したいと考えていた。
花城「出版社で働いていた頃から、出版がデジタルとのミクスチャーになる兆しをすごく感じていたんです。ミクシィから小説が生まれたり、ほぼ日のようにメディアファーストで後から書籍化されるような動きが出てきていましたから。
そんなとき、TUGBOATが雑誌ポータルサイト『magabon(マガボン)』を立ち上げた。ここならデジタルの可能性を探りつつ、自分の経験も活かせると思ったんです」
入社後はNTTドコモのiチャネルコンテンツのディレクターを担当。大手雑誌社と共にコンテンツを作るだけでなく、サイト内のデザインも担った。当時は端末もOSも多種多様だった時代。データ配信前には300台近い検証端末を並べ、デザインに崩れがないか目視で一つひとつ確認していたという。
花城「当時のiチャネルは、一度配信すると5000万人の手元に情報が届く。すごいんですよ、影響力が。あの時代ならではの勢いを感じられたのは、貴重な経験でしたね」
突然のフィリピン留学。国境を越えた“媒介者”へ
TUGBOATグループを卒業後、花城はフィリピンへ向かった。目的は語学留学。若干唐突な行動のように見えるが、氏の中にはある確信があった。
花城「グローバルで活躍する著名なクリエイティブディレクターから『YouTubeをきっかけにグローバルでヒットしている動画がある』という話をたまたま聞いて、衝撃を受けたんです。これからはグローバルで勝負できる人間にならないと勝ち目はないと感じて。少なくとも英語は必要だろうと思い、うだうだ迷うぐらいなら今行っちゃおうと」
仕事で英語を使った経験はない。語学学校では最下位クラスからのスタートだった。「thの発音だけを1時間やらされたのはキツかった」と本人は笑うが、時代の変わり目に本人が発揮した洞察力・行動力には、素直に驚かされる。当時、花城と同じように未来を予想し、行動に移せたビジネスパーソンはどれだけいただろうか。
一歩踏み出した人間の前には、相応しいステージが現れる。現地でフリーランスとして働きながら英語を学ぶ日々が三ヶ月ほど続いた頃、花城は「日本の大手企業がフィリピンで新規事業を立ち上げる」という情報を目にした。
これは新たなチャレンジの機会かもしれない──。「何の会社が、どんな事業をやるのか」さえ分からなかったが、花城は迷うことなく当時住んでいたバギオから担当者がいるマニラへ、片道7時間かけ会いに行った。
その事業が、DMMによるオンライン英会話事業だ。マニラで面接を受け、合格を知るとすぐに新オフィスがあるセブ島へ転居した。迷わず入社を決断できた理由をこう振り返る。
花城「オンライン英会話サービスは利用したことがあったので、その利便性を実感していました。シンプルに『この素晴らしいサービスを世の中に定着させたい』という想いが先でしたね」
意気揚々と新オフィスに向かったものの、そこでは全てがイメージと異なっていた。
花城「まず、オフィスがないんです(笑)。デザイナーとして入社したので、『新しいオフィスで、Macでグラフィックとか作るんだろうな』と思っていたんですが、まずはネット回線の配線から始めました。オフィスが完成した後は、講師を募集するための広告を出し、面接、トレーニングなどを日中に実施。DMMの人と連絡がつく夜の時間帯にサービスの設計やUI、LPの制作をしました」

「デザイナー」という肩書きはどこへやら。花城はここでも、縦横無尽に自分の役割を次々と変えていく。事業の成長とともに、その動きは、国境をも超えた。
花城「プロモーションに力を入れるタイミングになると、東京とフィリピンの『二拠点体制』に。タイアップやPRのために東京に行き、その成果が出てユーザーが増えると、またフィリピンに行って講師の採用活動をする繰り返しでしたね。
しばらくすると、海外初拠点となるリトアニア拠点の立ち上げを任されました。最初はフィリピンと同じように進めていたのですが、リトアニア講師にはクールな方が多かったため手厚いトレーニングが必要だと気づいて。まずはフィリピン講師の指導を受けてもらい、その後テストに合格したらデビューできる仕組みを整えました」
講師の採用やら教育といったオンボーディングはもちろん、時には「給料支払いの仕組み」や「拠点運営の方法」まで……。必要なものはなんでも作る。それを三ヶ月で一気にまとめあげたという。
話を聞けば聞くほど、花城がデザイナーであることをうっかり忘れそうになる。
花城「確かに、何の役回りだったのかはよくわからないですね(笑)。デザイナーとして貢献したというよりも、事業を伝え切るために何でもやった2年間でした」
当時を思い出しながら話す花城の表情は、苦労を超えた充実感を物語っていた。自身の熱量に素直な花城にとって、その時々に必要な役割を果たすことは、もはや自然の成り行きだったのだろう。
6000万DLのゲームアプリを生んだ、自然発生的なプロセス
フィリピンでDMMの新規事業に貢献する傍ら、花城は「ゲームアプリ開発」という未経験の分野にも挑戦していた。
きっかけは、ハッカソンで知り合ったトランスリミット創業者・高場大樹との出会い。世界で通用するカジュアルゲームの開発を目指していた。トレンドを理解するためにゲームを100個ほどダウンロードして毎日遊び、エンジニアを含めた3人でアイデアを出し合いながら開発を進めたという。「無償で趣味としてやっていた」と話す割には、一切の妥協が見られない。
そして2014年、リアルタイム対戦型脳トレゲームアプリ「BrainWars」をローンチした。なんと公開から1週間で100万DL、5ヶ月で500万DLを達成。アプリストアのランキングで2位に掲載された時期は、一日で20万DLに達する日もあったという。海外ユーザーからデザインを評価するコメントが多く届いたことは、デザイナーとしての自信にもつながった。
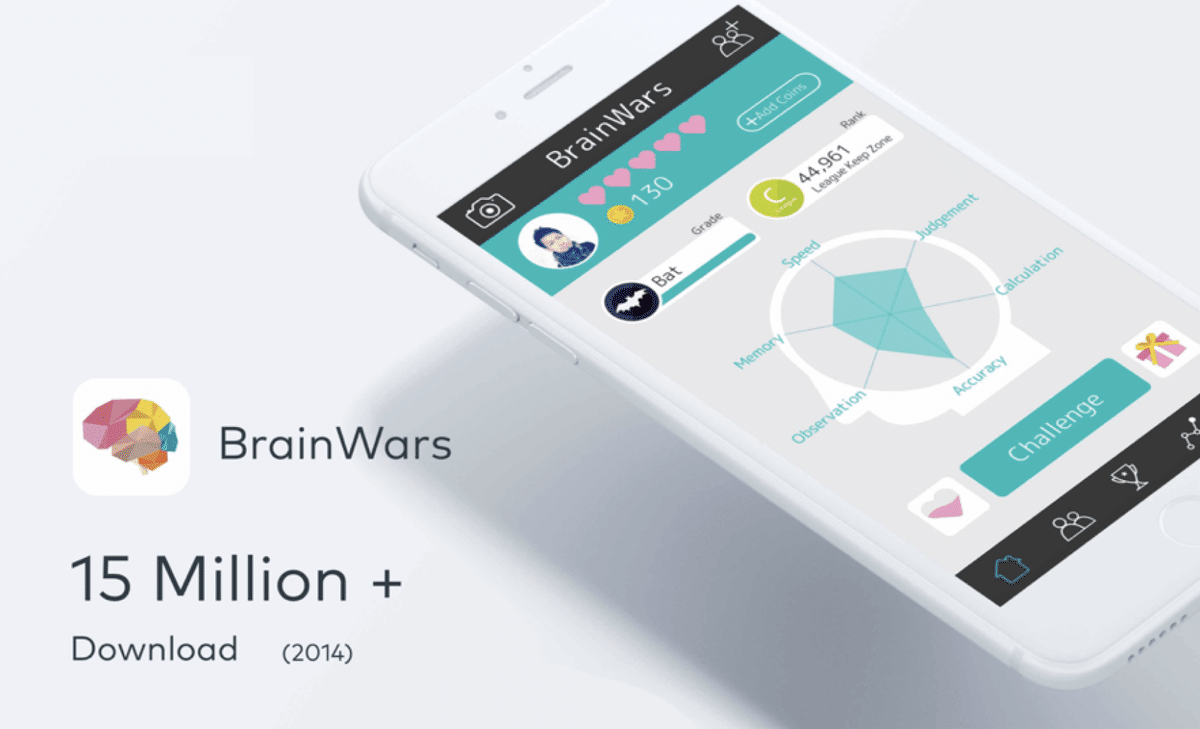
まもなくLINEからの出資が決定。「世界に挑戦するいいチャンス」と感じた花城は、2014年トランスリミットへ正式に転職。本腰を入れて取り組んだ第二作「Brain Dots」は前作に引けを取らない人気アプリとなり、DL数は両作合計で6000万を突破している。
つい怪物的な数字にばかり気を取られてしまうが、注目したいのはゲーム開発のプロセスだ。
花城「メンバーとランチに行くと、エンジニアが『Q』というゲームにはまっていたんです。10人ぐらいいたと思うんですが、みんな黙々と遊んでいたので、全然話が盛り上がらなくて(笑)。何がそんなに面白いんだろうと思ってよく観察していました。
その経験を踏まえ、自分たちでモックアップを作ったり、何度も対戦する内に、『みんなが黙々とやりだすのはこの瞬間だ!』という感覚がわかってきたんです。そういったモメンタムを生み出せたのは、観察やプロトタイピングといった、サービス作りにおける重要なプロセスを自然とやってこられたからだと思います」
花城をはじめトランスリミットのメンバーは、体系的にサービス作りのプロセスを知っていたわけではない。それにもかかわらず、極めて理に適った開発方法を選択してこられたのだという。
花城「今振り返れば、あれはオブザーブ(観察)だとか、それがヒューマンセントリック(人間中心)だったとかわかるのですが、当時の本人たちはそれに気づいていませんでした。スタートアップの生態系って面白いですよね。理屈から入っていない分、当時の自分たちには“熱”がありました」
クライアントの組織も“越境”
その後、花城はBCG Digital Ventures(BCGDV)へとフィールドを移す。ゼロから世界に通用するサービスを生み出した経験は、コンサルティングワークにも大いに活かされることになる。
花城「現・Dely CXOの坪田朋さんがいたことが、決断の要素として大きかったです。コンサル業界へのチャレンジというよりも、旗を掲げている人やその仲間と一緒に働きたいと思い転職しました」
スタートアップ中心だったキャリアの中で、今回はかなり毛色の違う転職に見える。しかしここでも、花城の越境する姿勢は、変わらないどころかより一層強化されたように感じられた。
花城「自分は確かにデザイナーを名乗ってはいますが、デザインだけを考えることはなく、クライアントのバックエンドやオペレーション、CS(カスタマーサービス)で行われるユーザーとの対話など、プロジェクトに関係するもの全てを把握します。その上でユーザーに『伝わってない』部分を洗い出し、課題を解いているイメージです。
関係部署には漏れなく関わり、業務を変える必要がある場合はメンバー一人ひとりを説得。デザインやUXに関係するメンバー全員を集めたディスカッションの場を設けて、横の連携がしやすい関係性の構築をサポートしたこともあります」

その事業特性上、具体の案件や詳細を明かせない部分もあるが、花城は常にクライアント組織の中を縦横無尽に動き回った。戦略策定やビジネスに強みを持つBCGと、プロダクトビルドやグロースに強みを持つBCGDVが両輪で動くことで、成果にコミットできているという肌感もあるという。
花城「BCGの存在があるから、場当たりの解決や部分最適ではない、戦略を伴ったアウトプットができます。お互いのケイパビリティが組み合わさることで、最小の力で最大の効果を発揮できるんです。
ちなみに、BCGDVはBCGとは異なる場所にオフィスを持ち、独自の組織やカルチャーで活動しています。お互いの独立性が担保されているので、絶妙な距離感がある。それが連携の潤滑油として働いている気がしますね」
ビジネスサイドと「対を成す」ための努力
現在はプレーヤーの立場を離れ、ディレクションの役割を担うことが多い花城。チーム内ではマネジメントを行う立場にあるが、最初の頃はマネジメントスキルを身につけるために、かなりの労力を費やしたという。
花城「メンバーが増えるにつれてチームのまとめ方を学ぶ必要性を感じて方々でインプットを重ねました。中でも影響を受けたのが、THE COACHでオンラインコーチングサービスを受けたことです。ここではテクニック以上にマインドセットに関する学びが大きかったです。大切なのは、相手を100%信じ切ること。リーダーがメンバーとの信頼関係を作らなければ、何も始まらないんだと気づきました」
その学びを活かし、花城はコーチングを担当、別のリードデザイナーがメンタリングを担当する体制でチームメンバーと向き合うことにした。花城は、メンバーが次のキャリアのために今やるべきことの相談に乗る。その一方でリードデザイナーは、そのキャリアを実現するために必要な具体的な技術をアドバイスする。
この2人の役割を、同じ人が担当しているケースも少なくないだろう。その場合、どうしても時間的・精神的な負担がかかりがちだ。また、技術的なフィードバックとメンタリングでは向き合うモードも異なる。それを二人に分散させることは負荷と効果双方の面で利が生まれている。
そして花城は現在、「Partner & Director」の肩書きを持つ。この肩書きが簡単に手の届くポジションでないのは周知の通りだ。高い評価を得るに至った理由を、花城はどのように捉えているのか。
花城「入社時にディレクターを務めていた坪田さんから『どんなにデザインが良くても、プレゼンスが高くなければ意味がない』と繰り返し言われていました。その影響を受けて『いかに組織内でのプレゼンスをあげるか』にこだわってきたのは一つの要因ではないかと思います。
例えば、ピッチの機会には積極的に手を上げましたし、ユーザーのストーリーを情熱的に訴えかけたり、ビジュアルで印象付けたりといった工夫を怠りませんでした。それに加えて、喋りの練習も徹底的に行いました。プレゼン本番の朝、近くのカフェでずっと練習している様子をメンバーに目撃されてしまったこともあります(笑)。「伝える」作業には、常にオーナーシップを持って取り組んできました」
また、デザインチームだけではなく、ビジネスサイドからも認められなければ、コンサルティングファーム内で一定の評価を得ることは難しいはずだ。この点に関しても、花城は徹底的に手を尽くしていった。

花城「言うまでもなく、BCGのメンバーは非常にロジカルです。リサーチ力も高く、マテリアルを何百ページも作ってくる。でも、相手が強いからこそ物怖じしてはいられません。きちんと対を成せるように、必要であれば自分も何百ページのマテリアルを用意することもありましたし、デザイナーならではのアドバンテージを出せるように、ピッチではできるだけプロトタイプを作って参加しました。会議では率先してファシリテーションを担当したり、役員に対してもバンバン意見を言ったりしてきましたね。
ビジネスサイドとは、それでどうにかイーブンだと感じています。今ではあらゆるシーンで声をかけてもらえるようになりましたが、それはこうしたアクションの積み重ねの結果だと捉えています」
こう聞くと、個別の要素でいえば「特殊」なものは存在しないことに気づかされる。ただ、花城はそれを「並外れた水準」でやり抜き「続けて」きたのだろう。
“越境するデザイナー”とは、組織の良き「媒介者」
ここまでの道筋を振り返ると、花城にとっては常に突き動かす「熱源」が存在してきた。今の氏にとってそれはなんなのだろうか。今後BCGDVで自身が果たすべき役割を聞くと、そのヒントとなる言葉が浮かび上がってきた。それが、「デザインの民主化」だ。
花城「デザイナーだけがデザインをする世界から、みんながデザインをする世界へとトランジションする必要があると思っています。本当にいいデザインを誰もが考えられるようになれば、自然とデザインは民主化されていく。それをサポートする媒介者になることが、我々の役目になっていくだろうと考えているんです」
方法論自体は存在する。デザインプリンシプルの制作やデザインツールの活用などもその一つだろう。中でも花城が最近深く掘っているものが「チーム内のコミュニケーション」だ。それは、自分自身が手掛ける仕事の本質に気付いたからだという。
花城「プロジェクトが終わると、クライアントから『花城さんのおかげでチームの中で繋がりができました』『意見を言い合える環境になって、新規事業を進めやすくなりました』という言葉をいただけることがあって。そのときに『自分の仕事の最後に残るのはカルチャーなんだ』と気付いたんです。
カルチャーというと軽く見られがちなのですが、組織にとっては一番大事なもののはず。なぜなら、閉塞感のある、心理的安全性の失われた土壌からは何も生まれないから。後でいろんなプロジェクトが豊かに育っていく大地になるよう、しっかりとカルチャーを耕すことが、自分の役割だと認識しています」

出版社で本を作っていた頃を振り返ると、ずいぶん遠くまで歩いてきた。時にはその肩書が分からなくなりそうにもなる道筋だが、それでも花城は「デザイナー」と名乗り続ける。それ故、デザイナーが発揮できる価値もより明確に意識している。
花城「改めてデザイナーってすごいと思うんですよね。みんなの考えを可視化することで議論を加速する力があるし、モチベーションがわっと上がるモメンタムを作ることもできる。そうしたスキルがあるからこそ、デザイナーは『良い媒介者』になれるんだと思います。
今の自分は何者かよくわからないと思うこともあります。それでもデザイナーとして培ってきたスキルは確かに役に立っている。これからもデザインに軸足を置きながら、あらゆる領域に越境し続けていきたいです。将来的には医療や教育など、デザインがまだ十分に浸透していない領域にもチャレンジしたい。そのとき、どんな化学反応を起こせるのか、自分自身楽しみにしています」
彼の行く先では、デザイナーの役割、そしてデザインの可能性をも越境し続けるのだろう。
花城泰夢は、これからも縦横無尽に自身の物語を紡いでゆく。

[文]一本麻衣[編]小山和之[写真]今井駿介
花城さんのプロフィールはこちらからご覧いただけます。

